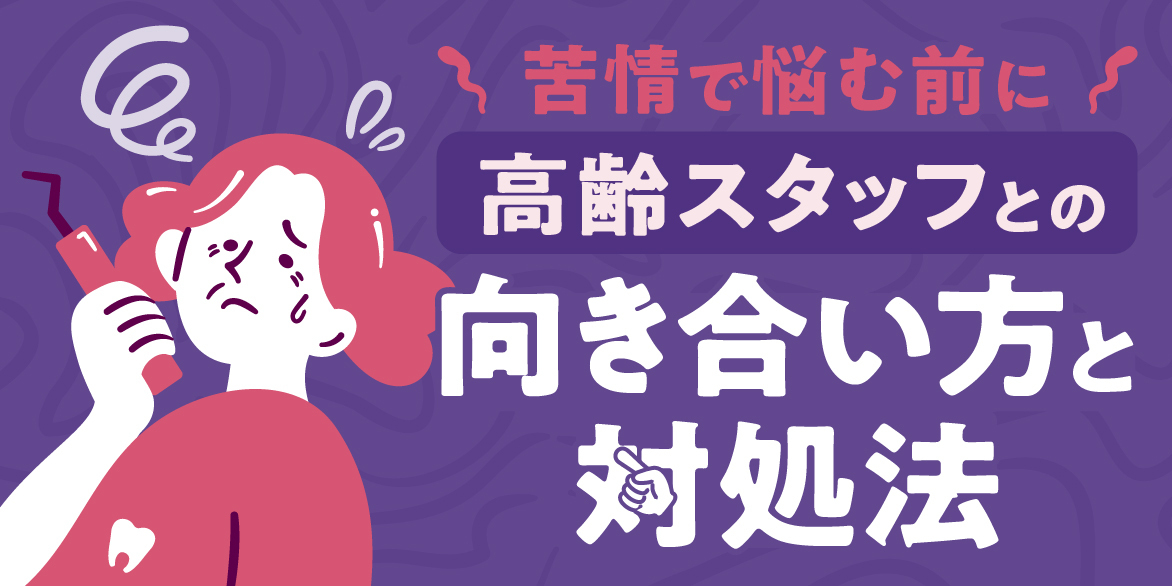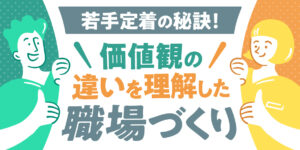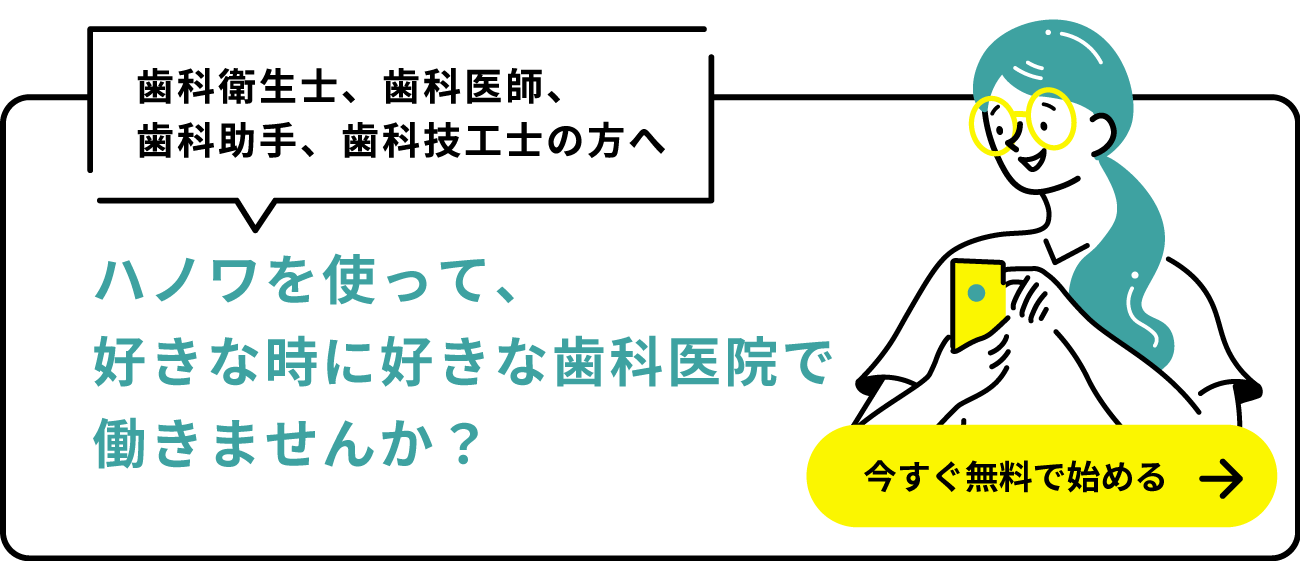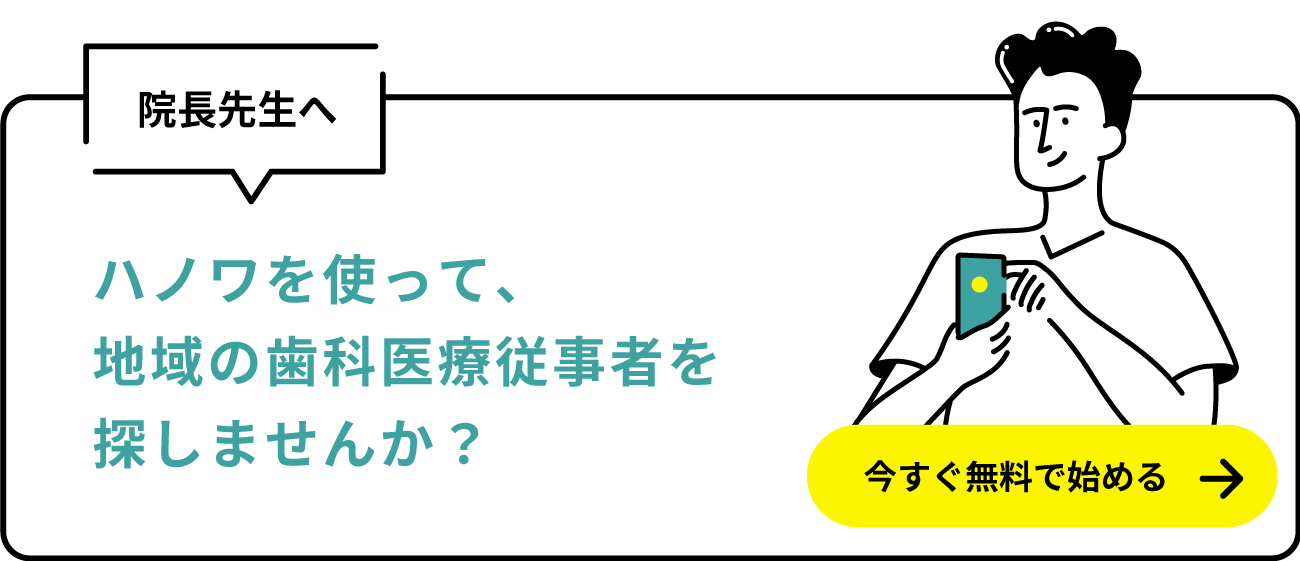- あの受付の方、
もう少し早く対応してもらえませんか? - 説明がよく聞こえなくて、
何度も聞き返してしまいました。
長年医院を支えてくれている
ベテランスタッフへの患者さんからの声に、
複雑な気持ちになったことはありませんか?
本人のがんばりや誠実さは十分理解している。
医院への貢献も計り知れない。
しかし、現実的な課題も見えてきている——。
そんな「高齢スタッフをどう支えるか」
に悩む院長先生へ、
具体的な対処法をお伝えします。
なぜ高齢スタッフは歯科医院にとって貴重な存在なのか
多くの歯科医院で
高齢スタッフが活躍し続ける理由は明確です。
| 信頼関係の深さ | 開院当初から医院を支え、 患者さんとの関係も 築いている |
|---|---|
| 安定した戦力 | 若手スタッフの 離職率が高いなか、 長期勤務してくれる 貴重な人材 |
| 豊富な経験 | 医療現場での 長年の経験と、 患者対応のノウハウがある |
多少の課題があっても、
「この人なしでは医院が回らない」
と感じる院長先生も多いはずです。
ただし、
歯科医院運営でもっとも大切なのは
患者さんの満足度です。
この点を見失わないよう、
バランスの取れた対応が求められます。
高齢スタッフに対してよくある苦情とは?
実際の医院で起こりがちな苦情をまとめると、
このようなものがあります。
対応スピードの問題
- 会計処理に時間がかかりすぎる
- 電話対応で長時間待たされる
コミュニケーションの課題
- 説明が聞き取りにくい、理解しづらい
- 時代に合わない対応で不快感を与える
院内への影響
- 若手スタッフがフォローに追われ、
業務効率が下がる - 説明や指導に時間を取られる
これらは決して悪意によるものではなく、
加齢に伴う身体的変化や
世代間のギャップが原因となることが
ほとんどです。
苦情を受けたときの3つの対処ステップ
まず大前提として、
すぐに辞めさせるのは
解決策ではありません。
それでは本人の誇りを傷つけてしまい、
職場全体の空気も悪くなります。
① 具体的な内容把握
曖昧な伝え方は避け、
事実に基づいた具体的な内容を伝えましょう。
| 最近、患者さんからの評判が 良くないようです。 | |
| 患者さんから「声が聞き取りにくい」 というご意見をいただきました。 一緒に改善方法を考えませんか? |
具体的な内容にして伝えることで、
本人も感情ではなく行動の問題として
受け止めやすくなります。
②改善可能性の検討
本人が「申し訳ない、気をつけるよ」
と前向きな姿勢であれば、
業務内容の調整や、伝え方の工夫で
対応できるかもしれません。
業務内容の見直し
- 電話対応や受付は若手が担当し、裏方業務に専念してもらう
- 会計処理には補助スタッフをつける
スキルアップの機会提供
- 接遇研修への参加
- 声の出し方や話し方の指導
③チーム全体の調整
高齢スタッフのフォローにあたる
若手スタッフが不満を抱えていると、
院内全体の温度差や不和に
つながることもあります。
定期的な面談やミーティングで、
全員が働きやすい環境づくりに
取り組みましょう。
継続雇用を成功させる3つのポイント
歯科医院の大切なスタッフである
高齢スタッフにこれからも
元気に働いてもらうために、
以下のポイントを意識してみてください。
①明確な契約条件の設定
65歳以上を継続雇用する際は、
以下の項目を明文化しておくことが重要です。
- 業務範囲
- 評価基準
- 雇用期間の見通し
これにより
「どこまで頑張ればいいのか」
「何が期待されているのか」が明確になり、
本人も医院側も
納得できる働き方が実現できます。
②業務の属人化防止
特定のベテランスタッフに依存しすぎると、
突然の退職や体調不良で
医院運営に支障をきたすリスクがあります。
- 業務マニュアルの整備
- 複数人での業務共有体制
- 後継者の育成計画
③ 定期的な評価と調整
年齢とともに体力や能力は変化します。
定期的な面談で現状を確認し、
必要に応じて業務内容を調整することで、
長期的な雇用継続が可能になるでしょう。
医院の成長段階として捉える視点
高齢スタッフの処遇に悩むということは、
歯科医院が長期安定運営を実現してきた
証拠でもあります。
ベテランスタッフへの感謝の気持ちと、
患者満足度への責任感——
どちらも院長としての誠実さの表れです。
- スタッフ全員が無理なく働ける職場環境
- 本人が誇りを持って働き続けられる
仕組み - 患者さんに安心して通院してもらえる
医院づくり
この3つを軸に、
“バランス”を取りながら進めていきましょう。
まとめ
少子高齢化が進む中、
今後は医療業界でも
シニア層の雇用機会が増加する可能性があります。
今のうちから高齢スタッフとの
向き合い方を学んでおくことで、
将来的な人材不足にも対応できる
医院づくりができるでしょう。
現在この課題に直面していない歯科医院も、
いずれ経験する可能性が高いテーマとして、
ぜひ参考にしていただければと思います。