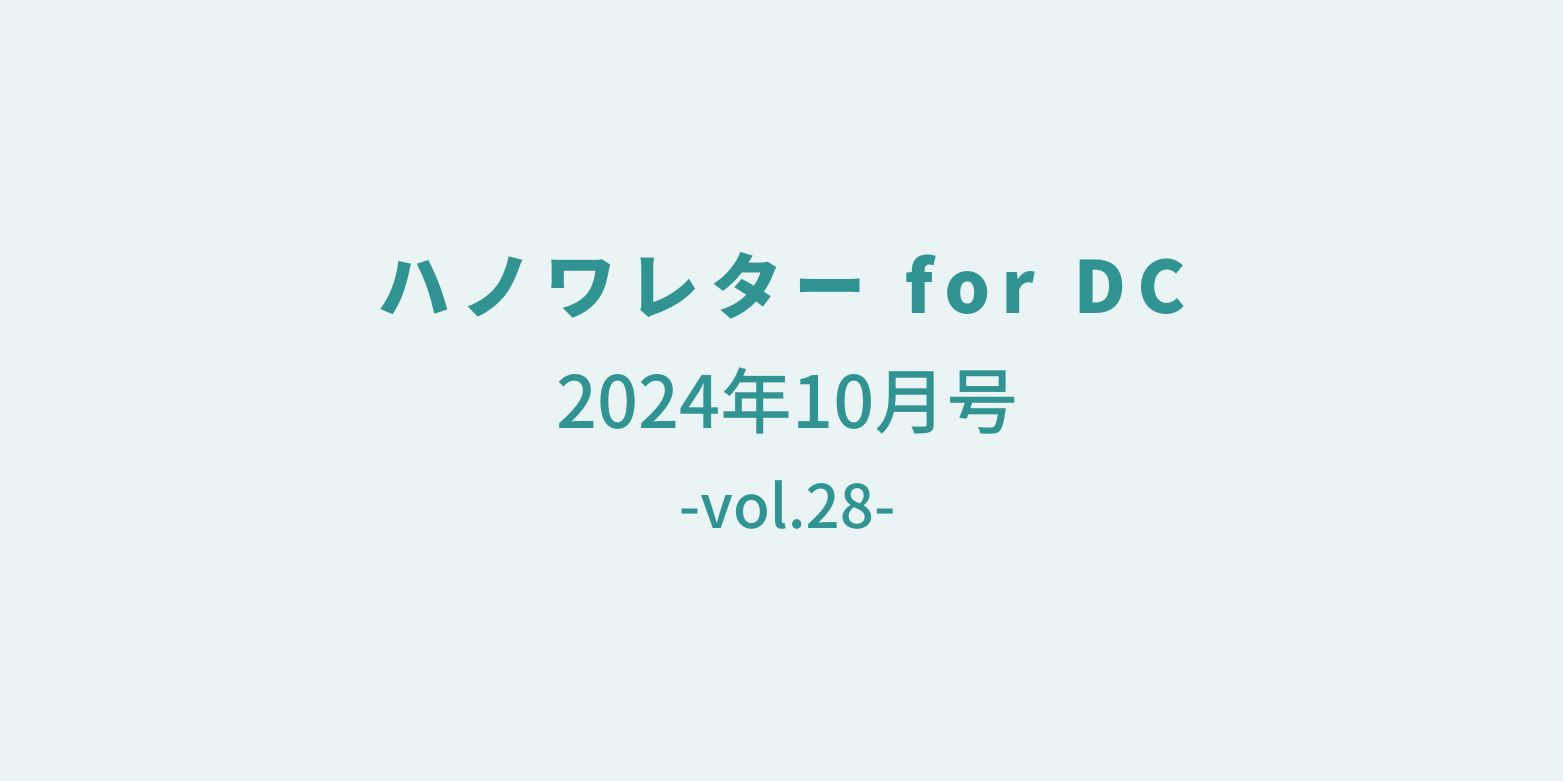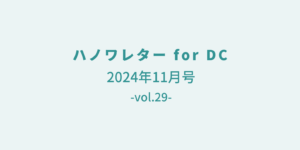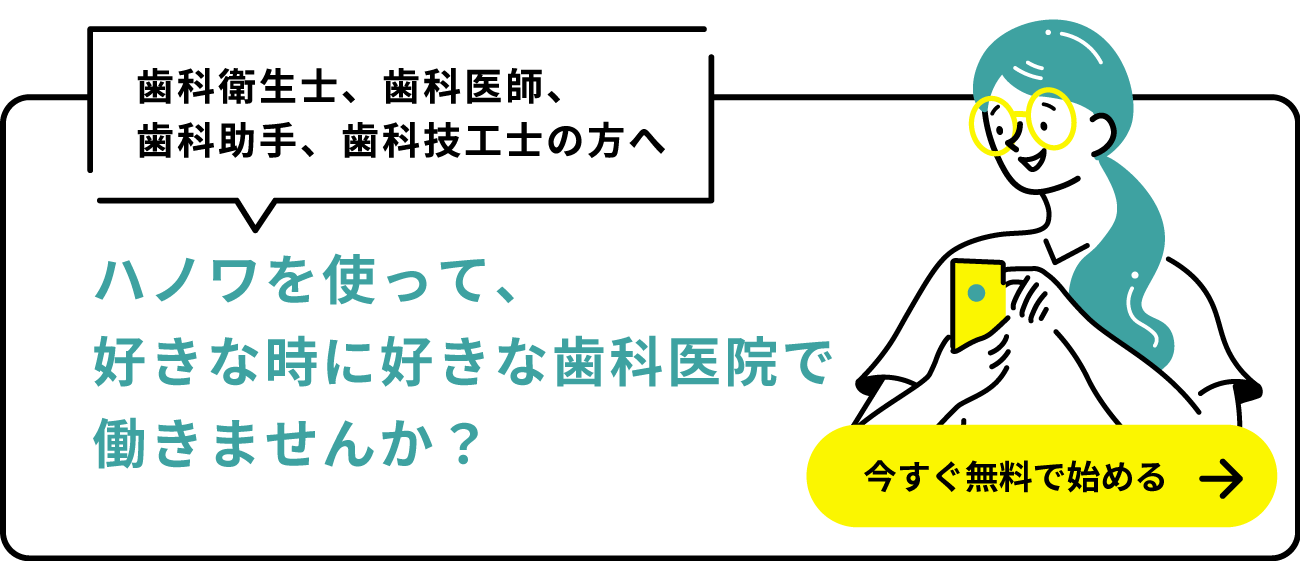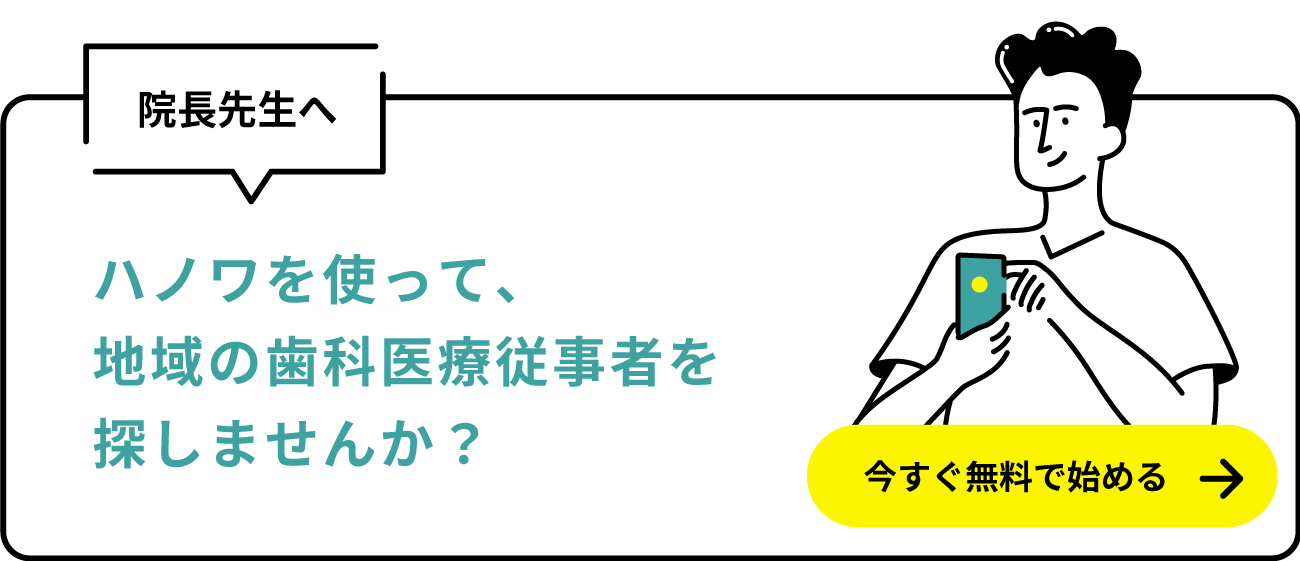こんにちは、ハノワの新井です。
9月にご利用頂いた全国726医院の皆さま
ありがとうございます!
このお手紙は
全国のHANOWAにご興味をお持ち頂いた
およそ4,000ほどの医院全てにお送りしています。
【保険診療とその健全性に関してあれやこれや】
会社とは何か?医療法人とは何か?
について最近よく考えます。
この夏に受けた研修の中で、
個人的には目から鱗な、
この辺りに関する知見に触れてきました。
これまで株式会社って何?合同会社って何?
医療法人って何?一般社団法人って何?
と思った方も少なくないと思います。
それらは要するに端的に言えば
2つのカテゴリーに分けることができます。
自益権と公益権です。
読んで字の如く、
自らを益する権利は更に2つに別れます。
「配当権」と「残余財産分配権」です。
公益権とは「議決権」のみです。
「配当権」とはその組織に出資した人たちが、
毎年の利益の中から配当を受ける権利を
指します。
「残余財産分配権」とはその組織を解散した際、
出資比率に応じて
残った財産を出資者に分配する権利です。
お察しのことかと思いますが、
平成19年以降に設立された医療法人には
この「残余財産分配権」は存在しません。
また、そもそも医療法人には
「配当権」も存在しません。
その研修では、
「配当権」「残余財産分配権」「議決権」
この3つによって
あらゆる組織は説明できる。
とのことでした。
詳しいことは会社法をご参照ください。
もう一つ。
経営学の大家のピーター・ドラッカーは、
著書「マネジメント」の中で
「公的機関のマネジメントは特に難しい」
と述べています。
なぜなら
「株式会社にとっての成果とは
顧客の創造である。
しかし、公的機関における成果とは、
より多くの予算の獲得に他ならない。」
と言います。
想像はつきますね。
役所の今年の予算が1億円なら、
年間経費を8,000万円に抑える
インセンティブがありません。
無駄と分かっていても
綺麗に使い切るか、「まだ足りない!」
と叫ぶことが常態化してしまいます。
なんとなく伝わりますでしょうか?
保険診療という仕組みの中で営む
全ての事業体を、
ドラッカーの言う「公的機関」
と例えるとします。
多くの場合その成果は、
被保険者に対する付加価値の創造ではなく、
より多くの医療費の獲得
になってしまうのではないか?
とも思えてくるわけです。
またドラッカーは、
公的機関のマネジメントを
更に難しくするのは、
利益を残すべきではないという性質
にも由来すると言います。
なぜならば、
公的機関のそもそもの売上や原資は、
ほとんどが税金や保険金だからです。
そもそもが税金で営まれているのに、
「医療法人として
今年は利益がたくさん出たから納税ができる!」
なんて言わなくていいんです。
だってそもそも税金でやってるんだから、
利益を成果指標にしてんじゃねーよ。
もっと意義あることに使えよ。
ってことです。
だから「配当権」も「残余財産分配権」も
無いんですね。
そう考えると株式会社は
成果を上げることも、
出資者の利益を保全することも
竹を割ったようにシンプルです。
自益権を最大化すればいいんです。
一方、医療法人が適切に成果を上げて、
ガバナンスを効かせながら出資者
(擬似的にこの場合は日本国)
の利益を保全するのって、
超絶難易度が高いです。
はっきり言って
お医者さんにできるとは
とても思えません
(思っても医者に向かって書くなよ…)。
このマネジメント難易度の高さと、人材不足は
論文ベースで研究があるかは知りませんが、
まぁ相関はありそうな気がします。
はぁ…。
課題の奥底を覗く程に、
何からすれば良いのやらと思えてきます。
株式会社HANOWA 代表取締役 新井翔平
▽過去のアーカイブはこちらから▽
▽ご意見・ご感想お待ちしております▽